錦嚢風月譚(きんのうふうげつたん) 清光が照らす真実 2025年 全36話 原題:錦囊妙錄
第5話 あらすじ「戻れぬ岸辺」
絡み合った嘘と血縁の糸は、ついに“真実の子”という残酷な答えへと辿り着く――。
夜の闇の中で捕らえられた李逢春は、刃を向けたまま斉夢麟に銃口のような視線を突き刺し、動くなと命じる。
羅疏は震える子供を抱き寄せ、県令の許しを得て一歩ずつ李逢春に近づく。
その足取りは慎重でありながら、決意に満ちていた。
「あなたがこの子に手を下せない理由――
それは、この子が“あなたの子”だからではありませんか?」
羅疏の言葉は、張り詰めた空気を切り裂く。
眉、目元、輪郭……
子供の顔は、驚くほど李逢春に似ていた。
否定しながらも動揺を隠せない李逢春の前に、林雄が現れ、かつて“噂を隠すための偽装結婚”の真相を語る。
未亡人となった李家の娘――
生活に困り果てていた林劉氏と、世間体を守るため“子供”を必要としていた林雄。
二人の利害が一致したことで結ばれた結婚は、愛ではなく、体裁のための契約にすぎなかった。
その告白は、李逢春の心を打ち砕く。
自分は崖から落ちて死んだと思われていたが、実は生きており、這うようにして戻って来たのだと語る。
だが帰郷した彼を待っていたのは、“すでに別人の人生を生きる妻”と、「子供は最初から林雄の子だ」という歪んだ噂だった。
真実を知らぬまま、裏切られたと思い込んだ李逢春は、復讐の刃を振るい、愛する妻を手に掛けてしまった。
そして、自分の血を引く子供にまで刃を向けていたのだ。
斉夢麟は激昂する。
「命を、こんなにも軽く扱うのか。
一人は人を“隠蔽の道具”として利用し、もう一人は、何も信じずに殺した――二人とも、男として失格だ!」
理想と現実の狭間で揺れてきた斉夢麟が、初めて“悪を憎む”という自らの信念を、はっきりと口にする瞬間だった。
翌日。
林雄は子供を連れて故郷へ帰る準備を進める。
「この子は、私が必死に求めた命だ。
大切に育てることで、自分の罪を償う」
そう語る林雄を、人々は相変わらず噂話で包囲する。
事実よりも刺激を好み、嘘を“真実”として語り続ける町の姿に、斉夢麟の心は沈み、羅疏もまた“人は変えられない”という現実を噛みしめる。
その一方、県衙の片隅では、金描翠が新しい生活に耐えきれず、大妈との衝突を繰り返していた。
些細な嫌味が、ついには殴り合いへと発展し、彼女の心は深く傷つく。
羅疏は希望を語り、「脱籍すれば、ここから出て、もっと良い生活が待っている」と励ますが、金描翠の胸には、“どこへ行っても同じではないか”という諦念が芽生え始める。
斉夢麟は羅疏の裁断の腕前に感服し、“通りがかり”を装って彼女を待ち伏せする。
羅疏はその嘘を承知しながらも、何も言わず、彼を遺体安置所へ連れて行く。
「ここだ」と告げ、中へ入った斉夢麟を外から施錠する――
羅疏流の、少し意地の悪い“試練”だった。
だがその帰り道、二人の前に立ちはだかったのは、鳴柯坊の“母親”――
羅疏と金描翠を連れ戻そうとする過去の鎖だった。
県令の制止により、二人は辛うじて県衙に留め置かれる。
その夜、金描翠は静かに決意する。
「……私は、帰る」
ここでの生活も、外の世界も、彼女にとっては、どこか居場所ではなかった。
“自由”の先にあるのは、希望か、それとも、さらなる孤独か――。
物語は、新たな別れの予感を孕みながら、静かに次章へと進んでいく。
第6話 あらすじ「川面に沈む秘密」
運命は時に、最も残酷な形で真実を突きつける。
そしてそれは、誰かの“目覚め”と、誰かの“後悔”を同時に生み出す――。
金描翠が静かに県衙を去ろうとするその時、斉夢麟は偶然にも彼女とすれ違う。
彼は羅疏が“密かに愛人を匿っている”と早合点し、苛立ちと焦燥のままに羅疏へ銀子を投げ渡し、「その者を追って金を持ち帰れ」と命じてしまう。
その横柄な態度は、羅疏の胸に、抑え込んでいた怒りを呼び覚ます。
貧しくとも必死に生き抜こうとする人々と、何ひとつ自らの力で築いたもののない斉夢麟。
彼女はこの青年に対し、初めてはっきりとした失望を覚えるのだった。
一方の斉夢麟は、理由もわからぬまま胸騒ぎに囚われ、軽率な思いつきから“恥をかかせるための薬”を買い、羅疏に飲ませようとする。
彼は遠巻きに彼女の様子を窺い続けるが、羅疏はただ黙々と水を飲み、やがて一人で川辺へ向かう。
そこで斉夢麟が目にしたのは、羅疏が靴を脱ぎ、その下に覗いた――刺繍の施された、明らかに“女物”の靴だった。
衝撃は雷のように彼の心を打つ。
羅疏が“女性である”という事実。
それを、斉夢麟だけが知らなかったのだ。
混乱と動揺のあまり、彼は足を滑らせて川へ転落し、岸辺に漂う“死体”を目にして悲鳴を上げる。
使用人たちに助け出された彼は、そのまま屋敷へと運び込まれる。
目を覚ました後も、斉夢麟の胸には後悔が渦巻く。
“自分は女性を大切にしてきた”――
そう信じてきたはずなのに、羅疏に向けてきた数々の言動は、女性であると知った今、あまりにも無神経で、傲慢で、浅ましかったのだ。
見舞いに訪れた羅疏を前に、斉夢麟は目を覚ましているにもかかわらず、気まずさから“眠ったふり”をしてしまう。
だが彼の従者は、「わざわざ来てくれたのだから、きっと怒ってはいない」と諭し、斉夢麟はようやく自らの未熟さを認めるのだった。
その翌日――
県衙は再び、不穏な空気に包まれる。
川から引き上げられた変わり果てた死体。
検死官は“溺死、死亡推定三日”と判断するが、羅疏は直感的に“殺人”であると確信する。
斉夢麟と羅疏は共に捜査に乗り出し、川辺での聞き込みから、「船を借りたまま返さなかった男」の存在に辿り着く。
その船から見つかった一本の簪――
そして、行方不明となっている若者・馮二郎。
馮二郎の家で見つかった香袋、港で聞き出された証言、かつて親しかった娘・梅娘、そして彼女を無理やり他家へ嫁がせようとする兄の存在。
点と点は、少しずつ“歪んだ恋と利害の鎖”として繋がり始める。
やがて浮かび上がる名は、教師・孟樵生。
彼の住まいから見つかる簪、そして似た香袋。
すべてが、川に沈んだ命と、隠された情事、そして取り返しのつかない選択へと収束していく。
斉夢麟は、捜査を共に進める中で、初めて“並んで歩く”という立場に立つ。
もはや、命令する者ではなく、共に考え、共に真実へ迫る者として。
川面に沈んだのは、ひとつの命だけではない。
それは、斉夢麟の未熟な自尊心と、羅疏への軽率な見下しでもあった。
真実は、すでに水底で、静かに彼らを待っている――。
第7話 あらすじ「沈黙の理由」
川に沈んだ一つの命は、人々の“秘密”と“名誉”を抱えたまま、まだ語られるべき真実を水底に残していた――。
羅疏と斉夢麟は、姿をくらました馮二郎の母を密かに尾行する。
そしてその読み通り、彼女は息子・馮二郎を匿い、逃亡の手助けをしようとしていた。
羅疏が近づいた瞬間、母は羅疏の足を掴み、「逃げろ!」と必死に息子へ叫ぶ。
斉夢麟はとっさに馮二郎を追い、ようやくの思いで取り押さえるが、縄を探す騒ぎの中、野次馬が押し寄せ、なぜか斉夢麟まで一緒に縛られてしまうという騒動に発展。
駆けつけた県令により、事態は何とか収拾される。
県衙へ連行された馮二郎は、「孟樵生を船に乗せ、殴った。だが彼は自ら川へ飛び込んだ」とだけ供述し、それ以上は何ひとつ語ろうとしない。
県令は彼を“致死の責を負う者”と断じ、十日後の斬首刑を宣告する。
だが羅疏と県令は感じていた。
馮二郎は、何かを“守るために”沈黙している――。
真実に辿り着くため、羅疏は侍女の装いで梅家へ赴く。
斉夢麟は自ら小僧役を買って出て、彼女に同行する。
梅紅英は、馮二郎が殺人を犯すはずがないと断言し、裁判への出廷を決意する。
だが、法廷で彼女が何度問いかけても、馮二郎は沈黙を守り続ける。
兄は“家の名誉”を守るため、この事件を口外しないよう周囲に口止めを頼むが、梅紅英はその“沈黙”こそが、さらに馮二郎を追い詰めていることに気づいていた。
羅疏は梅紅英の兄の動向に疑念を抱き、あの夜どこにいたのかを問いただす。
兄は「工房で働いていた」と答えるが、梅紅英は涙ながらに訴える。
「兄が私と馮二郎の仲を引き裂かなければ、こんなことにはならなかった」と。
やがて、再び面会に訪れた梅紅英の必死の説得によって、ついに馮二郎は重い口を開く。
――あの夜。
彼は梅紅英と“駆け落ちの約束”をしていた。
梅紅英の寝床に忍び込んだ彼が連れ出したのは、布団に包まれた、裸の孟樵生だった。
怒りと裏切り、屈辱と絶望が一気に噴き出し、彼は孟樵生を殴りつけた。
だが、その“恥辱の真実”こそが、馮二郎が語れなかった理由だった。
川に沈んだのは、ただの命ではない。
それは、“言えない真実”と“守られるべき誰かの名誉”だったのだ。
沈黙の裏に隠された、あまりにも苦く、あまりにも痛ましい真実が、ついに姿を現し始める――。
第8話 あらすじ「借刀の罪」
沈黙は、誰かを守るためにあるのか。
それとも、誰かを壊すためにあるのか――。
羅疏と県令は、馮二郎は真犯人ではないと断言する。
梅長雄と陸晏如――
事件当夜のアリバイを主張する二人のうち、どちらかが必ず嘘をついている。
そう確信した二人は、真相を暴くため独自の調査へと動き出す。
斉夢麟は彼らの不在に気づき、迷うことなく後を追う。
県令は急用で引き返し、羅疏と斉夢麟の二人で梅家へ向かうこととなる。
梅家で出迎えたのは陸晏如。
彼女は、梅紅英の学業を監督するために書斎に出入りしていたと説明し、孟樵生とは簾越しにしか会っていないと主張する。
だが羅疏は、そこに残された“香袋”に違和感を覚える。
やがて現れた梅紅英は、陸晏如が嘘をついていると告発する。
自分が授業をサボるたび、二人きりになる時間が生まれていた――
それは疑念ではなく、確信に近い叫びだった。
追い詰められた陸晏如は、「名誉を失うくらいなら死んだ方がまし」と自ら命を絶とうとする。
羅疏の機転により一命は取り留められるが、梅家の中には、言葉にできない歪みが深く沈殿していく。
その後の調査で、陸晏如の実家には彼女の確かなアリバイがあること、一方、梅長雄の“工房でのアリバイ”は思い込みに過ぎないことが判明。
さらに斉夢麟は、川辺の船に残された爪痕と、孟樵生の爪に付着していた泥と木屑の符合に気づく。
点と点が、静かに、しかし確実に繋がり始める。
やがて梅長雄は、長年知っていた妻・陸晏如と孟樵生の不倫を認める。
陸晏如もまた、「家が没落していなければ、彼とは結婚しなかった」と冷酷な真実を吐露する。
激情の中、梅長雄は彼女の喉元に手をかけるが、「これで孟樵生のもとへ行ける」という言葉に、手を緩めてしまう。
そしてついに明らかになる真相。
偶然にも二人の不倫を知った第三者が、梅紅英と馮二郎の関係を“利用”し、“借刀殺人”という残酷な策を仕組んでいたのだ。
守るための沈黙は、誰かの人生を守ると同時に、誰かの人生を壊していた。
馮二郎は釈放され、梅紅英は彼を迎えに走る。
深く、強く抱き合う二人の姿は、失われかけた未来が、ようやく息を吹き返した証だった。
だがこの一件は、羅疏と斉夢麟に、“真実を知ること”の重さと、“正しさの代償”を、静かに刻み込んでいく――。
第9話 あらすじ「遺言と酒の香」
人の“想い”は、文字になった瞬間から、誰かを守る“証拠”にも、誰かを裁く“刃”にもなる。
静かな朝。
羅疏は焼売を作り、県令に振る舞おうとしていた。
通りかかった斉夢麟は、それが自分の好物であることに気づき、内心複雑な思いを抱くが、羅疏は意に介さない。
焼売を囲む和やかなひとときの中、県令は羅疏の意外な才覚――囲碁の腕前を知り、二人は“君”と呼び合う私的な距離で碁盤を挟む。
さらに県令は、羅疏の琵琶の話題に触れるが、羅疏は「今はもう弾きたくない」とだけ答える。
彼女の過去と、胸の奥に沈んだ事情が、言葉の隙間から静かに滲み出る。
その穏やかな時間を切り裂くように、喬家から訃報が届く。
酒蔵を切り盛りしてきた喬如蕙が急死したのだ。
何慎微は、遺体を早々に棺に納めようとするが、妹・喬若蘭はこれに激しく反発。
姉は何慎微に殺されたのではないかと主張し、県令に徹底した再調査を求める。
検死官と羅疏の立ち会いによる検視の結果、喬如蕙は病死であり、毒や外傷の痕跡は見当たらない。
さらに何慎微は、喬如蕙の筆跡による正式な遺言書を提示する。
そこには、酒蔵を何慎微に託すという内容が記されていた。
喬若蘭は激しく反発する。
「何慎微は婿養子。 酒蔵は本来、喬家の血筋が継ぐべきものだ」と。だが遺言書の存在は重く、県令は酒蔵を何慎微のものと認める判決を下す。
判決後、何慎微の酒蔵には暗い影が落ちる。
秘伝の酒“金蕊酒”の仕込みを控える中、喬若蘭が職人たちを連れ去ったことで、酒造りは頓挫の危機に陥っていた。
「姉が本当に酒蔵を譲るつもりなら、 なぜ秘伝のレシピを残さなかったのか」
――喬若蘭の疑念は、
相続争いではなく、“姉の死の真相”へと向けられていた。
羅疏は、喬若蘭が職人を引き抜いた理由が、復讐でも強欲でもなく、“姉の異変を知りたい一心”であることを見抜く。
幼い頃から二人きりで育ち、深い絆で結ばれていた姉妹。
頻繁に交わしていた手紙――
それらが、姉の急死に対する疑念をさらに強くしていたのだ。
羅疏は、「その手紙を見せてほしい」と告げる。
遺言という“文字の証拠”と、手紙という“心の証拠”。
どちらが真実を語るのか――。
酒の香りに包まれた喬家で、新たな謎が、静かに、そして確実に動き出していた。













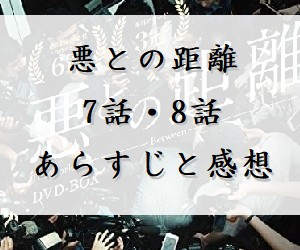
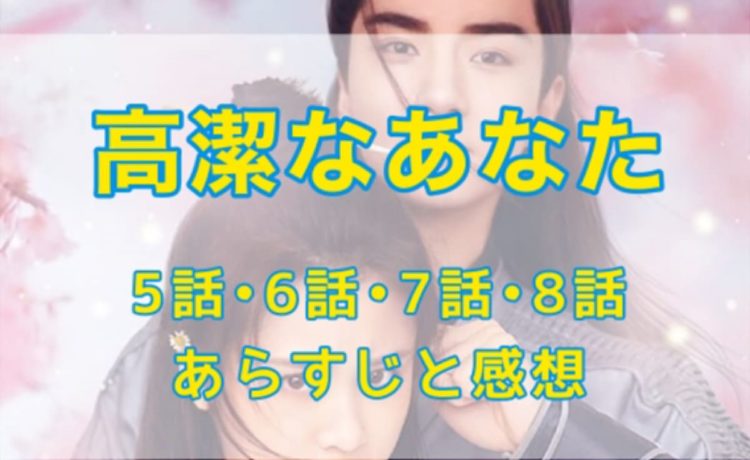
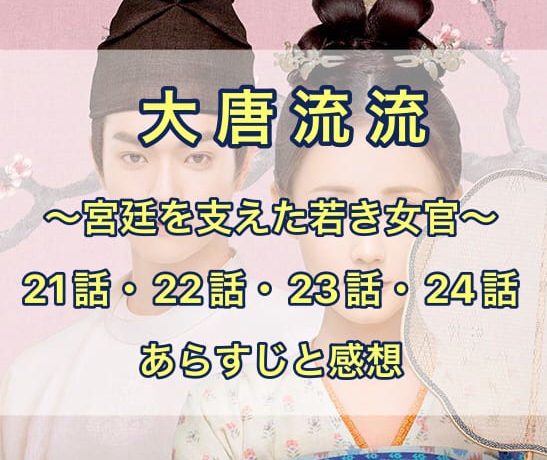


この記事へのコメントはありません。